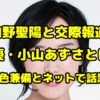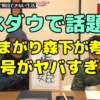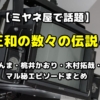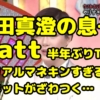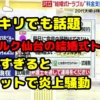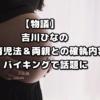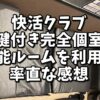【とくダネで話題】深夜ドカ食いは危ない!「夜食症候群」とは?
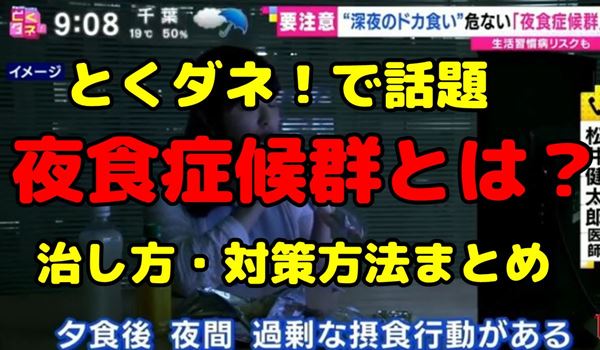
夜食症候群について2019年5月14日放送のとくダネ!で話題に。
医療ジャーナリスト・伊藤隼也さんが「夜食症候群の症状や対策方法」について解説していました。
私自身、夜食は結構食べていて気になったので、放送内容と治し方についてメモ代わりに記事にしました。
Contents
過食症に近い病気?夜食症候群とは?症状や特徴
夜食症とは1日の摂取カロリーの25-50%を夕食後に摂ってしまうことを言います。
- 成人男性の場合=夕食後に約570キロカロリー以上。
- 成人女性の場合=夕食後に約440キロカロリー以上。
夕食後に上記のカロリー以上を摂ってしまっていると夜食症の恐れがあるそうです。
松井健太郎医師によると「摂食障害の一部で、過食症に近い病気と考えられています。夕食後、夜間に過剰な摂食行動がある。(一日の摂取カロリーの)25~50%以上の(カロリーの)食べ物を食べること。」と番組でコメント。
番組では59歳夫の深夜のドカ食いを紹介
番組に出ていた夜食症候群の人(59歳男性)は、夕食後もカフェオレやあんぱんを食べて、さらにポテチやせんべい、アイス、果物なども食べて、合計1050キロカロリーも夜食だけで食べていました。
夜食症候群になると…
夜食症候群になるとホルモンバランスが崩れ、様々な病気を引き起こす原因になるそうです。
- メラトニン減少→不眠症の恐れ
- レプチン減少→夜間も食欲衰えず
- 朝の食欲減少→集中力低下
夜食症候群が慢性化すると、メタボリックシンドロームや糖尿病などの生活習慣病のリスクも高くなります。
夜になると食欲が止まらないのはなぜ?理由を解説!
夜食症候群を治すには?夕食後の対策方法5つ+αまとめ

- 歯磨き→自分の意志に区切りをつける
- 入浴→眠くなるように体を温める。
- ホットミルクやハーブティー(特におすすめ)→リラックスし眠気が増す
どうしても夕食後に食べたい場合は…
- うどんやおかゆ→脂っこいものは厳禁。
- 無塩のナッツ→医療ジャーナリスト・伊藤隼也さんはいつも食べているそう。
医療ジャーナリスト・伊藤隼也さんや、小倉智昭さんは対策としてナッツ類をポリポリ食べているそうです。
その他の方法
他にも薬物療法や認知行動療法といった治療方法もあるようです。
治療は食生活の状態を詳細に聞くことから始め、ストレスの根源を探り、抗うつ薬を使った薬物療法を試みる。加えて、認知行動療法で摂食欲求を強めているストレスに対する受け止め方を変え、それを取り除いていく。
止まらない夜のドカ食い「夜食症候群」という摂食障害
※YouTubeで過食の治し方を解説している動画がありましたのでこちらも参考にどうぞ。
【とくダネ!まとめ】夜食症候群の特徴と対策法
- 夜食症候群とは?→過食症に近い病気。一日の摂取カロリーの25~50%以上を夕食後に摂ってしまうこと。(※成人男性=570キロカロリー以上、成人女性=440キロカロリー以上)
- 夜食症候群が悪化すると?→生活習慣病のリスク増。最終的には、狭心症、心筋梗塞、脳血管系疾患の恐れ。
- おすすめの治療法は?→夕食後にホットミルクやハーブティーを飲む。
とくダネ!ではこんな感じで放送していました。
夜食症候群について少しでも参考になれば幸いです。
それでは!